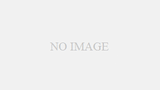今回も、前回の引き続きで『心理職の職業倫理』の話(心の健康の専門家としての倫理観)をします。
今回は、紹介するのは第3原則。
『相手を利己的に利用しない』。
これも、最初に読んだ時は「それは当然だよな」って思っていたんです。
相談者は、自分の問題を解決したいと思って来るわけで、利用されたいと思って来るわけではありません。
また、心に関する支援を受けに来るわけで、物を買いたいわけではない。
それなのに「この壺を買うと健康になりますよ」とか「この宗教を信じると全ての問題が解決しますよ」なんて言われたら「うわぁ〜騙されたぁ!」って思いますよね。
私だったら、そんなところは二度と行きません。
そして、家族や知人には「あそこは行かない方がいいよ」って教えます。
でも、WEB上では言いません。
「営業妨害だ!」って訴えられると困るので。
…え〜っと…何の話でしたっけ…
あぁ、そうそう。
『相手を利己的に利用しない』って話でした。
それで、これは職業倫理として当然の話だよなぁって思っていたんです。
最初は。
でも、説明を読んでみると、こんなことが書かれていたんです。
勧誘(リファー等の際に、クライエントに対して特定の機関に相談するように勧めること)を行わない。
(引用元『公認心理師の職責』/野島一彦編/遠見書房/2018/P 49/表1職業倫理の7原則)
ちなみに『リファー』とは、元々は「言及する」とか「参照する」という意味ですが「難しい問題の判断を専門家などへ委ねる」という意味でも使われます。
つまり、前回の第2原則とも関係がありますが、自分の範疇を超える問題が起きた場合に、よりふさわしい専門家に委ねるということです。
例えば、公認心理師も臨床心理士も『心に関する専門家』ではあっても、精神科の医者ではありません。
心に関する病気は、精神科の医者が治療にあたります。
つまり、精神科医のように薬を処方したりすることはできないんです。
ですから、もしもクライアントから「全く眠れません。何か薬を下さい」と言われても「医者にいって下さい」としか言えないわけです。
心理療法として、眠り易くなる方法なら教えられると思いますけど。
そして、私が気になったのは、その時に特定の機関に相談するように勧めてはいけないということ。
つまり「このクライアントの問題は心理職の範囲を超えるものだ」と判断した場合に、他の専門家に委ねることになりますが、その時に「どこが良いとかは言えませんので、ご自分で探して行ってください」としか言えないと言うことです。
言い方によっては「あとは、勝手に自分で探して、専門家を見つけてね」って、サジを投げたように思われないのだろうか。
「やっと信頼できる人に出会えたと思ったのに見捨てられた」と思わないだろうか。
そんなことを思いました。
特定の機関を勧めたって、そこから紹介料をもらうとかさえしなければ、利己的に利用したことにならないのではないかと思うんですけど…
難しいものですね。
自分の専門的な行動の範囲で支援をしなきゃいけないから、それを超える場合は、他の専門家に委ねないといけないけど、その専門家を紹介するわけにはいかないなんて。
まぁ、私が公認心理師になるのは、早くても3年先ですから、それまでにじっくり悩んでみたいと思います。
先生に相談したりしながら。
うつ病に伴う悩みや心配ごとなど、まずは気軽に、ご相談ください。
[contact-form-7 id=”8101″ title=”お申し込み簡易バージョン”]